介護のマメ知識
公開 / 最終更新
認知症による帰宅願望への効果的な対応とは?原因や対策について解説

認知症の高齢者の症状の一つとして「帰宅願望」があります。施設に入所したての認知症の利用者様には特に強く現れ、対応や声掛けに悩む介護職員の方も多いのではないでしょうか。この記事では、帰宅願望の原因とともに具体的な対応例について解説します。皆様の日々のケアに活かしていただけることを願っております。
1分で予約・お問い合わせ完了♪
目次
帰宅願望とは?
「家に帰らせてください」と訴えたり、荷物をまとめて玄関に向かったりすることを「帰宅願望」と呼びます。施設の中だけではなく、自宅にいるのに「帰りたい」と訴えることもあります。このような行動を駆り立てる原因について解説します。
帰宅願望は認知症の症状の一つ
認知症の中核症状には記憶障害や見当識障害、判断力の低下などがあり、脳の萎縮によって引き起こされます。
帰宅願望は、中核症状に不安や環境の変化といった要因が重なることで引き起こされるBPSD(周辺症状)です。そのため、施設に入所して間もない頃は、環境の変化や新生活への不安に適応できず、帰宅願望を引き起こしていると考えられます。
帰りたい先は自宅とは限りません。故郷や家族などの親しい人々を指している場合もあります。
また帰宅願望は単に「家に帰りたい」という欲求に留まりません。その背後にある本人なりの理由を理解し、安心できる環境を提供することが大切です。
帰宅願望は悪いことではない
介護職員として強い帰宅願望を訴える利用者様がいらっしゃると対応に困ってしまうことも多いと思います。
しかし帰宅願望は悪いことではありません。誰でも慣れない場所では緊張したり、不安を感じたり、帰りたいと思うこともあるのではないでしょうか。
見当識や判断力が低下した利用者様にとって「帰りたい」という訴えの裏には、その方なりのさまざまな理由が隠されていることもあります。まずは利用者様の訴えに耳を傾けてみることで対応のヒントがわかるかもしれません。
帰宅願望が起きる要因
帰宅願望が引き起こされる原因はさまざまですが、主な要因とされているのが「不安」です。環境の変化であったり、自身の健康上の問題であったり、家族の安否であったりと、高齢者はさまざまな不安を抱えています。
記憶障害や見当識障害によるもの
記憶障害や見当識障害といった認知症の症状によって、自身の置かれている状況や時間、場所に対する認識がわからなくなることが原因の一つです。入所に至った経緯を記憶できず、現状の不安を解消できないため、同じ訴えを繰り返します。しかし、記憶障害によって少し前の出来事を忘れてしまっても、感情は保たれ、不安や怒りを引き起こした理由はわからなくとも、その時のつらい感情は心に影を落とし、興奮や帰宅願望となって現れます。
夕暮れ症候群
夕方の、外が暗くなり始める頃に、「帰って夕食を作らないといけない」「子どもを迎えに行かないといけない」など、過去に何度も繰り返してきた行動に引っ張られ、帰宅願望が発現するケースも多くみられます。「これ以上遅くなると、暗くなって帰れなくなる」といった焦りも影響していると考えられ、これらの症状は「夕暮れ症候群」と名付けられています。
環境の変化
住み慣れた環境と異なり、知らない人に囲まれての生活は高齢者にとって大きな負担です。また、職員が忙しそうに動き回っているのを見ていると、利用者様も落ち着かず、安心できません。このような不安をかき立てる環境の変化が帰宅願望を引き起こす原因となります。
帰宅願望への対応の仕方

帰宅したいという気持ちを否定せず、気持ちに寄り添う
不安から帰宅願望を訴える利用者様に、「帰れませんよ」と頭ごなしに否定するのは逆効果です。さらに不安を与えてしまい、症状を強めてしまうこととなります。「○○さん、何かお困りですか?」「どちらに行かれますか?」など、行動の原因を聞き取り、心情に寄り添った声掛けを行いましょう。
知らない場所で知らない人々に囲まれている状況は、認知症の方に大きな孤独を与えてしまいます。孤独を解消できるようなコミュニケーションが大切です。
なるべく一対一で対応する方が良いでしょう。大勢に囲まれると、緊張や恐怖から興奮しやすくなります。
安心できる話題や行動による場面転換で関心の方向を変える
家に帰りたいという思いや孤独といった感情を理解した上で、一緒にフロアを歩いたり、静かな場所へ案内しましょう。場所が変われば気分も変わることはよく見られます。
帰りたいという思いを直線的に消そうとするのでなく、相手の気分をゆっくり変化させ、落ち着いた状態にすることが重要です。ご本人が好きだった趣味の話や得意料理などを伺い、ご本人から教えていただく姿勢で会話をしましょう。そして、帰りたいという訴えや言葉に注目するのではなく、ご本人自身への関心をもった会話を心がけることで、利用者様は、おきようのない「不安」から、自分自身の存在を認められ、ここに居て良いんだという「安心」に変わり、心の落ち着きへと変化させることができます。
環境要因を取り除き、整える
私たちは居心地が良いことも悪いことも正確に伝えられますが、認知症によって見当識や判断能力が低下すると、感じているのに伝えられなかったり、不快の原因が本人にもわからなかったりします。光や音に過敏に反応して、ストレスを感じている場合もあります。特に白内障を患っていると、白い光を眩しく感じやすいため、ブラウンやイエローに調光すると良いでしょう。
また、外が薄暗くなると夕暮れ症候群が起きやすくなります。「夕方になるので一緒にカーテンを締めましょう」などと時間を加えた言葉をかけ、暗くなってからではなく、うす暗くなる頃に早めにカーテンをひき、照明をつけて明るくしましょう。
部屋のインテリアには利用者様の好きなものを飾るなど、居心地の良い空間を演出できるように気を配ります。家族の写真を飾るのも非常に効果的です。
居場所や役割をつくる
入所当初は知らない場所で落ち着かず、帰宅願望を訴えることも多いと思います。しかし、何年経過しても訴えが減らない利用者様は、自分の居場所がないと感じているのかもしれません。利用者様同士や職員とのコミュニケーションを積極的に取れるような雰囲気づくりで不安を減らすことが大切です。
また、何らかの役割を提案することも効果的です。洗濯物を畳んだり、掃除を手伝ったりと、誰かと一緒に作業をしていることで、コミュニティの一員であることを認識し、大きな安心と自信につながります。
利用者様が落ち着いて過ごせる定位置にソファーなどを用意するのも良い方法です。利用者様にとって安らげる生活スタイルの構築を目指しましょう。
行動を制限しない
荷物を持って玄関を出ようとする利用者様を、力ずくで止めようとしてしまうこともあるのではないでしょうか。施設によっては日中玄関の施錠をしていない所もあり、万が一利用者様が外に出てしまうと安全の保証が難しくなります。
ただし、施錠をすれば問題が解決するわけではありません。鍵がかかっていることを知ると、施設に対して強い不信感を抱いてしまうこともあります。
以前筆者の勤める施設では、数時間にわたって玄関を離れようとしない利用者様がいましたが、思い切って一緒に外へ出てみると、「今日は違うみたい」とおっしゃり、ほんの10分ほどで施設に戻られました。行動を制限しないこと自体が解決策になる場合もあります。
あいまいな対応をしない
忙しいあまり、つい「あとで自宅まで送ります」「車を回すのでここで待っていてください」などその場限りの対応をしてしまうこともあるかもしれません。
その言葉をぼんやりと覚えていて、別の職員が「帰れませんよ」などと言ってしまうと、利用者様からすれば「騙された」と感じ、さらに不信感を募らせてしまいます。
認知症の方の対応として目指すべき目標は、不安や焦りを緩和し、穏やかな表情で過ごせることです。利用者様にとって居心地の良い生活というのは、一朝一夕ではできません。普段の行動を観察したり、帰宅願望を引き起こす原因を調べたりして、一つひとつ時間をかけて対応することが大切です。
帰宅願望が出た時の具体的な対応事例

ここからは実際の対応事例を2つ紹介します。まったく同じように行う必要はありませんが、ポイントも解説いたしますのでぜひ参考にしてください。
①帰宅願望の方の気分を変えた事例
A様はリビングでテレビをご覧になっていましたが、突然「家に帰る」とおっしゃいました。「帰りたいのですね。帰る前に、少しだけ手伝ってもらえますか?」と声を掛け、洗濯室に案内しました。タオルを一緒に畳みながら「料理はお好きですが?」「得意料理は何ですか?」「今うちにキャベツが余ってるんですが、どうしたらいいですか?」など、A様が好みそうな話をします。
タオルを畳み終えたら「手伝ってくださり、ありがとうございます」と感謝を伝え、リビングへお連れします。そして、いつも一緒にいる他の利用者様を示して「あの方をご存知ですか?」と尋ねました。「知っています」とおっしゃり、自分からその方の横に座られ、笑顔で手を握りあっておられました。「もう少しで夕食の準備ができますから、ここでお待ちになりますか?」とA様に伝えると、首を縦に振ってくださりました。
ポイントとしては、まず相手の話を聞いて復唱することです。自分の要望を理解してくれていることが相手に伝わります。
そして役割の提供です。特に余ったキャベツなどの具体的な相談をすることで、自分が相手に対して胸襟を開いていることを認識させます。
興味のある話で快刺激を促し、手伝っていただいたお礼をしっかりと伝えることも大切なポイントです。最後に顔なじみの利用者様に会うことで不安な気持ちも薄らいだことでしょう。帰りたいのは自宅ではなく「不安が和らぐ場所」だったのです。
②居場所作りの事例
B様は2年前から施設に入所していますが、「家に帰らせてほしい」と毎日職員に訴えます。ぬり絵がお好きと聞いていましたので、ぬり絵のレクリエーションにもお誘いしますが、落ち着かない様子ですぐに席を立たれてしまいます。
よくよくお話を伺うと、家族がどうしているのか心配とのことでした。奥様は病院に入院されており、時々はお見舞いにも行かれていますが、記憶障害により覚えておらず、「妻はどうしているのか」と心配なご様子でした。
B様のカンファレンスの中で、ある職員が「前に外出した時の景色を覚えていた」との発言があり、視覚からの記憶が残りやすい方ではないかとの仮説が立てられました。そこで、奥様のお見舞いに行かれている時の写真を家族様に依頼し、写真立てに入れて飾りました。
その後、帰宅願望はほとんど見られなくなり、ぬり絵にも集中することができて、他の利用者様や職員との会話も増えるようになりました。奥様の状況を写真から思い出せるようになったことで落ち着いた生活を取り戻すことができました。
まとめ
帰宅願望は、さまざまな不安要素が重なることで起こる認知症の症状です。しかし、適切な対応を続けること、環境を整えることなどで症状は軽減できます。「どう説明したら理解してもらえるのだろう」と言葉での説明に執着せず、利用者様の心の訴えをしっかりと聞き取り、声掛けや周辺環境調整など多角的な面から工夫をし、不安を取り除くための対策が必要不可欠です。この記事が皆様のケアの一助となれば幸いです。
この記事をシェアする
人気記事ランキング
Ranking
ALL
週間
カテゴリー
Category
人気のキーワード
Keywords














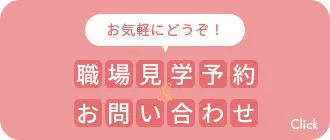





白ゆり介護メディア編集部
いかに白ゆりの魅力を伝えるかを常日頃考えている介護メディア担当です。
白ゆりの魅力と一緒に、介護職の皆さんのプラスになる知識やお悩みの解決につながる情報も発信しています。