介護のマメ知識
公開 / 最終更新
わかりやすい介護記録の書き方|場面別の例文、効率的に書くポイントを解説

介護記録の作成は、介護サービスを提供する上では重要な業務です。
しかし、「文章を書くことが苦手」「他の業務で忙しい」などの理由で、介護記録を書くことに負担を感じる介護職員も少なくありません。
今回は、介護記録の書き方について、わかりやすく説明します。
介護記録を書くことに苦手意識や負担を感じる介護職員の方は、ぜひご覧ください。
1分で予約・お問い合わせ完了♪
介護記録を書く目的
そもそも介護記録は何のために書くのでしょうか。
介護記録を書く目的は、以下の通りです。
- 介護職員間の情報共有
- 利用者様やご家族とのコミュニケーションツール
- ケアプランへの反映
- 万が一のときの法的な証拠
介護記録を書く際、上記の目的を意識しながら書きましょう。
介護職員間の情報の共有
介護現場では、介護職員・看護師などの多職種が業務上必要な情報を共有し、利用者様にさまざまな介護サービスを提供しています。
しかし、日々の勤務体制や業務内容には変動があり、職員が集まって情報を共有する機会を作ることが難しく、口頭での情報共有は正しい情報が伝わりにくいです。
このような場合、介護記録に必要な情報を書き残し、職員が閲覧することによって、滞りなく職員間の情報共有ができます。
そのため、結果的に利用者様の安全を守り、よりよい介護サービスの提供につながります。
利用者様やご家族とのコミュニケーションツール
介護記録は利用者様やご家族とのコミュニケーションツールとして役立ちます。
例えば、介護施設に入居する利用者様のご家族は、面会時でしか普段の様子を知ることができません。
そのため、「どのように過ごしているのか」「ちゃんとお世話になっているのか」不安に思うご家族も中にはいらっしゃいます。
このような不安を解消するためには、利用者様の健康状態や日々の様子を書いた介護記録をもとに、ご家族へ詳しく伝えなければなりません。
利用者様やご家族とのコミュニケーションツールとして役立つように、読みやすい介護記録を書くことが求められます。
ケアプランへの反映
介護現場ではケアプラン(介護サービス計画書)に基づき、利用者様にとって適切な介護サービスを提供するため、定期的にケアプランの内容に沿ったサービスを提供されているか確認しなければなりません。
特に、以下の3つを介護記録に書き残すことにより、重要な情報として今後のケアプランに反映されます。
- ケアプランに沿ったサービス提供ができているのか
- ケアプランに沿ったサービスを提供した際の反応・満足度
- サービスを提供したその後の変化
ケアプランによって、利用者様・ご家族からの満足度や信用にも関係するため、ケアプランの支援内容を意識しながら介護記録を書きましょう。
万が一のときの法的な証拠
介護現場における法的なトラブルから身を守る目的で、介護記録を書く必要があります。
介護保険制度ではサービス提供時の記録が義務となっており、利用者様に何らかの事故が発生した場合、以下の3つを介護記録に書き残さなければなりません。
- 事故の経緯
- 利用者様の状態
- 職員の対応
このような内容を介護記録に書くことにより、訴訟などのトラブルに発展した場合でも適切な対応を行った法的な証拠となり、身を守ることができます。
そのため、事故が発生した際、詳しい内容を介護記録に書くことが求められます。
介護記録の基本的な書き方
介護記録の基本的な書き方を理解することにより、介護記録を書く上で必要なスキルを身につけることができます。
ここでは、4つの介護記録の基本的な書き方について、詳しく説明します。
短い文章で簡潔にまとめる
介護記録を書く際は、短い文章で簡潔にまとめるように心がけましょう。
短い文章にまとめると、介護記録が読みやすくなったり、正しい情報を分かりやすく伝えることにつながります。
例えば、「~で、~で」と接続詞を多用した長文の場合、記録が読みづらくなり、何を伝えたかったのかという意図を汲むことが難しくなります。
このような場合、接続詞の多用を控える・一つの文章に一つの情報のみ書く「一文一義」を意識し、文章を区切ることがおすすめです。
介護記録を書く際は、短い文章で簡潔にまとめる工夫が必要と言えるでしょう。
専門用語や略語は控える
介護記録は利用者様・ご家族が閲覧する場合があり、専門用語や略語が多い介護記録では、内容・意味が伝わりにくいです。
また、さまざまな職種が介護記録を閲覧した際、専門用語や略語が多い介護記録では、職種によって内容の理解度に差が出るため、情報を共有することが難しくなる原因となります。
特に介護職員として経験年数が長い人ほど多用する傾向が強いため、専門用語や略語をできる限り控えて、分かりやすい表現・言葉で書くことを心がけましょう。
使ってはいけない表現・言葉に注意
以下のような表現・言葉には特に注意が必要です。
- 侮辱や差別的な表現
例:「バカ」「しつこい」「勝手に~をした」「わがまま」など - 命令や指示の表現
例:「~させる」「~させた」など - 不快に感じる専門用語
例:「徘徊」「不穏」「介護拒否(抵抗)」など
例えば、利用者様・ご家族が閲覧した際、上記のような表現や言葉が並べられた文章を読むと、ショックを受ける方や不快に思う方もいます。
その結果、利用者様・ご家族からの信用・信頼を失うことになるでしょう。
介護記録を書く際は、読む方の気持ちを考え、ソフトな表現に置き換えながら分かりやすい介護記録を書きましょう。
ありのままの事実を書く
介護記録を書く際は、実際に見たり聞いたりした、ありのままの事実を書くように意識すると、誤解を与えず正しい情報を伝えることができます。
例えば、「○○さんは不機嫌そうな表情をしていた。」と書いた場合、職員の自分目線で感じた憶測であり、本当に不機嫌だったかは利用者様本人でないと分かりません。
しかし、「○○さんは険しい表情をしていた。」と書くと、見たままの事実として、正しい情報を伝えることにつながります。
しかし、無意識にのうちに自分目線で感じた事実や憶測を介護記録に書くこともあるため、注意が必要です。
場面別の介護記録例文

これまで、介護記録を書く目的や基本的な書き方について解説しましたが、具体的にどのように書けばいいのか、気になるのではないでしょうか。
本章では、以下の4つの場面における介護記録を書く際の観察すべきポイントと例文を解説します。
- 食事場面
- 排泄場面
- 入浴場面
- トラブル場面
ぜひ、参考にしてください。
食事場面の介護記録の例文
食事場面における介護記録を書く際、観察すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 咀嚼(食べ物を噛む)と嚥下(食べ物を飲み込む)の動作
- 食器と箸を使う動作
- 食べている時の姿勢と表情
- 食事のペース
- 食事・水分の摂取量
また、利用者様の状態に合わせて、以下の食事に関わるポイントも観察しましょう。
- 食事の際の体調・空腹感
- 服薬の際の様子
- 食事への不満・悩み
食事は利用者様の健康状態に大きく関わる生活行為であるため、上記のポイントを観察し、客観的な事実に沿って、詳しい内容を書くことが必要です。
書き方の例文
7:30 朝食を提供。主食5割・副食4割、食事とともに提供したお茶100㏄程摂取。
昨日の朝食の摂取量と比較すると、食事・水分摂取量が低下している。
「今朝の食事の内容はいかがでしたか?」と尋ねると、「味は美味しいけど、あまりお腹が空いていなくてね。お腹が溜まっている感じがする。」との返答。
もともと便秘がちで服薬による調整を行っていた事を考慮し、看護師へ報告・相談し、引き続き、食事と水分摂取量・排便の有無の確認を行い、便秘が続く場合、看護師から医師へ相談することに決まる。
排泄場面の介護記録の例文
排泄場面における介護記録を書く際、主に以下のポイントを観察しましょう。
- 排泄の頻度・時間帯
- 排泄物の性状・色・量
- トイレの使い方
- トイレを使う際の身体動作(便座の立ち座り・トイレ室内での方向転換など)
- 衣類の着脱動作
- おむつ使用時の協力動作(寝返り・腰を上げる・拭き取りなど)
また、利用者様の状態に合わせて、排泄に関わる以下のポイントも観察しましょう。
- 下剤や利尿剤などの服薬状況
- 排泄の際の体調
- 紙パンツ・紙おむつの使用状況
排泄も利用者様の健康状態に関わる重要な生活行為であるため、詳しい内容を介護記録に書き残しましょう。
書き方の例文
14:00 排泄介助を実施。
本人居室からナースコールがあり訪室、「トイレに連れて行ってください。」と希望されたため、車椅子へ移乗しトイレへ案内。
車椅子からトイレへの移乗の際、手すりをつかみ自力で立位を保持しながら職員による介助によってズボンを下ろす。
便座へ座った後「終わり次第ナースコールを押して教えてください。」と声をかけ退室。
その後、トイレ室内からナースコールがあり退室。
トイレ便器内に水様の便を確認、本人へ「お腹の痛みなど、体の調子は悪くないですか?」と尋ねると、「お腹は痛くないし、大丈夫。すっきりした。」との返答。
排泄介助後、本人より「ちょっと疲れたから部屋で休みたい。」と希望されたため、居室内へ戻り、ベッドへ横になる。
入浴場面の介護記録の例文
入浴場面における介護記録を書く際、主に観察すべきポイントは、以下のとおりです。
- 皮膚の状態
- 体型(やせ・肥満度)
- 感染症の有無
- 入浴中の体調
また、以下の入浴に関連する動作も確認しましょう。
- 体を洗う動作
- 頭を洗う動作
- 湯船への出入りの動作
- 衣類の着脱動作
入浴中は利用者様の全身状態や身体機能などを観察できる重要な機会であるため、細かく観察した上で、介護記録を書きましょう。
書き方の例文
10:00 浴室にて入浴。普段は自分で背中を洗うが、「今日は右肩が痛くてタオルを背中に回して洗いにくいので、手伝ってほしい。」と希望があり背部の洗身介助を行う。
右肩の腫れや内出血などは見られず、職員より「他の所も洗いましょうか?」と尋ねると、「胸や足とかは自分で洗えるから大丈夫。」と言われ、痛みがない左手で胸・足を自分で洗う。
湯船に入った際、「体が温まったから右肩の痛みが和らいだ。」と笑顔で話す。
寒さによって肩の痛みが出た可能性や今後も肩の痛みが発生する可能性があるため、看護師・介護職員間で情報を共有し、様子観察となる。
トラブル場面の介護記録の例文
介護現場では移動中の転倒やベッドからの転落、食事を食べている際の窒息など、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
場合によってはトラブルが発生した際の経緯や事実確認を行うため、ご家族や自治体への報告や記録の開示を求められることもあります。
そのため、トラブルが発生した場合、先ほど解説した5W1Hを意識し、トラブル発生時の様子・職員の対応を客観的な視点で書くことが必要です。
書き方の例文
22:00 居室からナースコールによる呼び出しあり訪室。
ベットの横の床で座り込み、ナースコールのボタンを押したままの状態になっている本人を確認。
「トイレに行こうと思ってベッドから立ったけど、足元がふらついてしまい、そのまま座り込んでしまった。」とのこと。
「尻もちをついてしまったから、お尻が痛む。」との事で、看護師へ状況を報告。
看護師訪室、お尻を中心に全身の状態を確認、内出血や腫れなどの外傷はなし。
お尻の痛みについて「今は良くなった感じがする。」と話した後、職員の介助によって立ち上がり、ベッドへ戻る。
看護師から本人へ、明日の朝まで様子を見て、痛みが強い場合や身体機能が著しく低下した場合、ご家族と相談して病院受診をすることを提案。
本人「分かりました。迷惑かけてすみません。」と同意。
介護記録を効率的に書くポイント
分かりやすい介護記録を書くことは重要ですが、時間や手間をなるべく減らし、効率的に介護記録を書くことも重要です。
ここでは、介護記録を効率的に書く3つのポイントを詳しくご紹介します。
常にメモ帳を持ち歩く
介護記録を効率的に書くためには、常にメモを持ち歩き、業務中に起きた出来事を書き残しましょう。
日々の業務に追われると介護記録を書く時間を確保できず、後からまとめて介護記録を書く時には、内容を忘れてしまうことがあります。
さらに、内容を忘れてしまった場合、思い出すまでに時間がかかります。
このような場合、メモを常に持ち歩き、業務中の出来事・利用者様の状態を書き残すと、介護記録を書く時間を短縮できるため効率的です。
さらに、メモの情報を介護記録に書くことにより、介護記録自体の正確性を高める結果にもつながります。
テンプレートを作っておく
テンプレートとは定型文のことで、介護現場での食事・入浴・排泄など、職員が関わることが多い場面ごとにテンプレートを作ると、介護記録を書く効率を高められます。
例えば、食事の場面で活用できるテンプレートは、以下のとおりです。
○○ ○○ 様 (利用者様の氏名)
○○○○(タイトル どの様な内容の記録なのか)
00:00 ○○(場所)にて食事。○○、○○、○○(献立名)はご自身で召し上がる。
主食〇割・副食〇割・○○(水分の種類)は○○○㏄ほど召し上がる。
食事について尋ねると、「○○○」(利用者様の言動)とのこと。
介護ソフトを利用している場合、テンプレートの活用は効果的で、使用するソフトによってはあらかじめさまざまなテンプレートが実装されたものもあります。
しかし、利用者様の状態や環境によって、テンプレートに当てはまらない事も発生するため、過度に頼りすぎないようにしましょう。
良く使う表現や言葉をまとめておく
介護記録を書く時によく使う表現や言葉をまとめておくことも、効率よく書く方法の一つです。
例えば、文章を書くことが苦手な人の場合、頭では状況を理解していても、どのような文章表現で書けばいいのか分からなくなり、手が止まる事もあるでしょう。
このような場合、利用者様の様子・状態などでよく使う表現や言葉をメモなどにストックすることで、効率的に介護記録を書くことができます。
介護記録を書く時に活用しやすい表現の具体例には、以下のようなものがあります。
- 気分:憂鬱そうな様子・活気がない様子・落ち着かない様子
- 顔色・表情:血色がよい・青白い・むくんでいる
- 状態:満足そうな様子・意欲的な様子・くつろいだ様子
- 食事:一気に・ゆっくりと
- 睡眠:うとうと・寝言を言う・ぐっすり
- 呼吸:浅い・荒い・早い・深い
また、分かりやすいと思える上司・先輩の書き方を真似することによって、介護記録を書く上での効率やスキルを高める効果があるため、おすすめです。
白ゆりグループではICT化で介護記録をさらに効率化

タブレット端末でテンプレートを使って入力
白ゆりグループの介護記録は、すべてタブレット端末で行っており、手書きでの記録の時から、介護記録にかける時間が1/7に減りました。
また、使う表現や文章はテンプレートから選ぶことができるので、記録に慣れていない方、タブレット端末が不安な方も簡単に入力できます。
職場見学も実施しています
白ゆりグループでは、応募する・しないに関係なく各施設で職場見学ができます。
タブレット端末での介護記録を含めた業務効率化や職場の雰囲気を見に来てみませんか?
少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度、施設の見学にお越しください!
スタッフ一同、皆さまのお問い合わせをお待ちしています♪
まとめ
介護記録を書く目的は、職員間の情報共有や利用者様・ご家族とのコミュニケーションを円滑に行うなどの目的があります。
また、介護記録の書き方には以下のような方法があるため、介護記録を書く目的と合わせて意識しながら書くと、今までよりも介護記録が書きやすくなるでしょう。
- 短い文章で簡潔にまとめる
- 専門用語や略語は控える
- 使ってはいけない表現・言葉に注意
- ありのままの事実を書く
さらに、効率的に介護記録を書き、時間・手間を軽減できるように、以下の方法を日々の業務で実践することがおすすめです。
- 常にメモ帳を持ち歩く
- テンプレートを作っておく
- よく使う表現や言葉をまとめておく
そのため、介護記録は目的・書き方を意識しながら効率的に書くように努めましょう。
この記事をシェアする
人気記事ランキング
Ranking
ALL
週間
カテゴリー
Category
人気のキーワード
Keywords




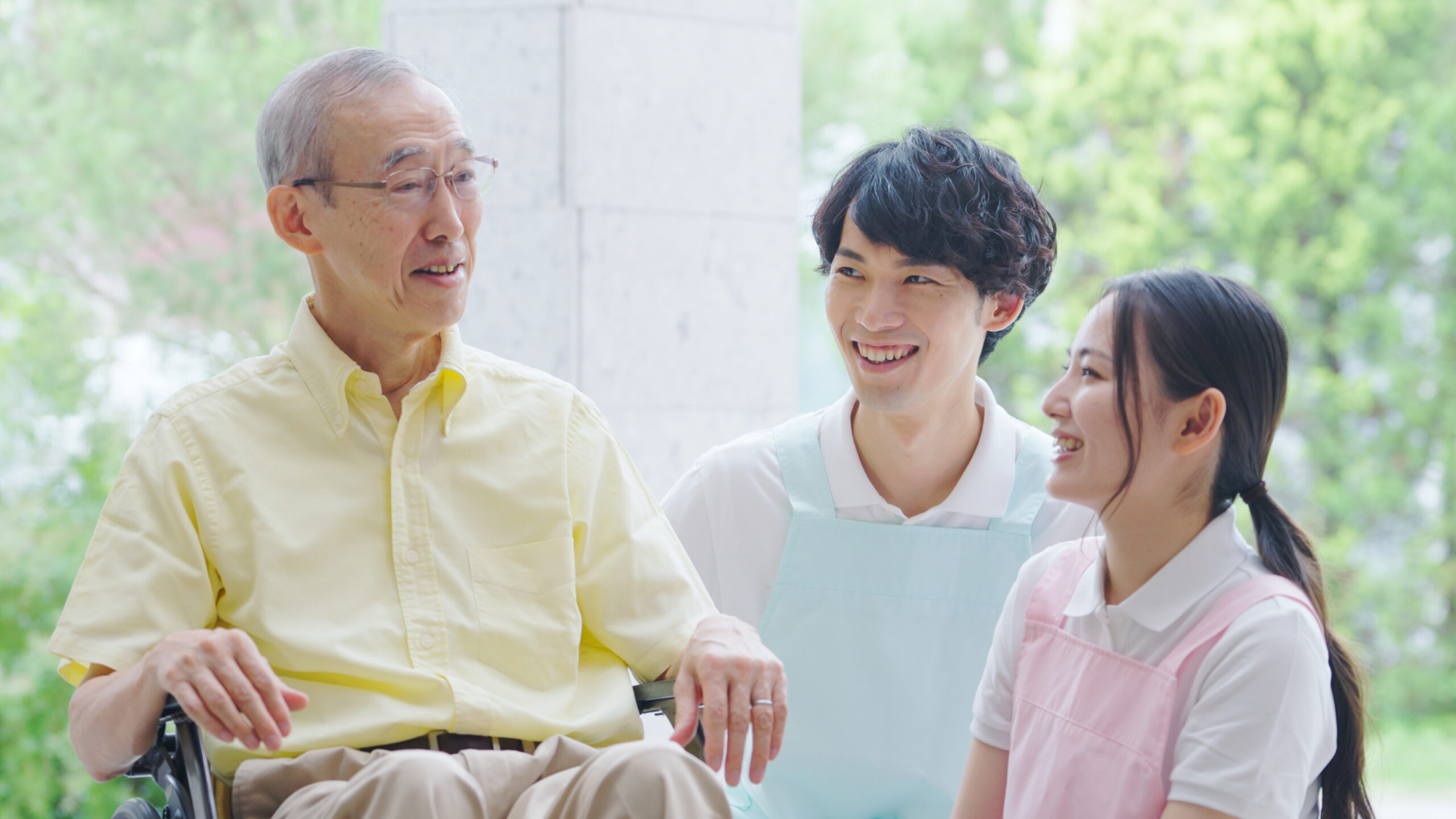









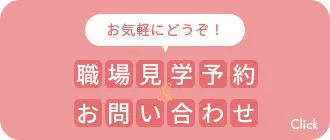





白ゆり介護メディア編集部
いかに白ゆりの魅力を伝えるかを常日頃考えている介護メディア担当です。
白ゆりの魅力と一緒に、介護職の皆さんのプラスになる知識やお悩みの解決につながる情報も発信しています。