介護のマメ知識
公開 / 最終更新
高齢者とのコミュニケーションや会話のコツは?相手に寄り添うために大切なこととは
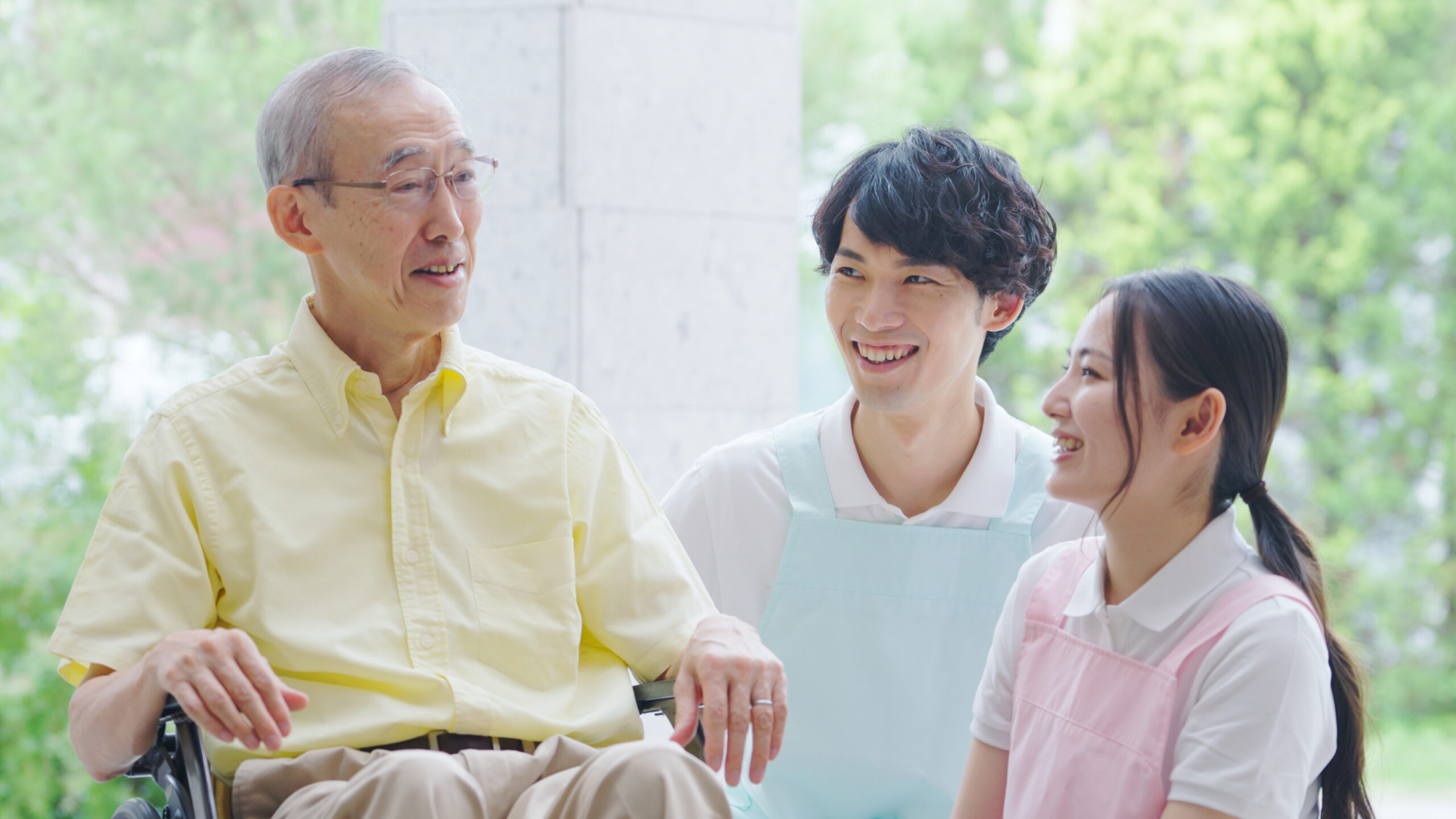
介護現場では高齢者とのコミュニケーションがとても大切です。しかし、高齢者の中には、認知症や脳梗塞で話すことが難しい方や難聴の方もいらっしゃいます。そのため、「どうすれば上手くコミュニケーションが取れるのか?」と悩む方も少なくありません。
この記事では、高齢者に寄り添ったコミュニケーションを取るためのポイントや留意点を事例と共にご紹介します。
現場で働く介護職の方、介護職を目指している方の参考になれば幸いです。
1分で予約・お問い合わせ完了♪
目次
高齢者とのコミュニケーションが大切な理由
高齢者とのコミュニケーションは、なぜ大切なのでしょうか?
質の高い介護サービスを提供するには、利用者様との信頼関係の構築が重要です。そのためには相手に寄り添ったコミュニケーションを取る必要があります。
また、利用者様とのコミュニケーションには以下の目的もあります。
- 表情や会話から利用者様の体調や精神面の状態を確認する
- 利用者様の小さな変化に気づき、生活環境や日常生活での困りごと、対人関係、詐欺被害等のトラブルやアクシデントを未然に防ぐことができる
- 感情や思考に刺激を与え、脳の活性化や認知機能の低下予防につながる
- 信頼関係の構築ができ孤独感の解消や生きがいや安心感、満足感を与える
利用者様の体調や精神面の変化を確認
コミュニケーションは単なる会話ではなく、以下の事例のように、利用者様の体調確認や精神面の変化を確認するための大切な時間でもあります。
【事例】ある朝の介護施設での介護職員AとK様・D様との会話
①K様との会話
職員A:「K様、おはようございます。体調はいかがですか?」
K様 :「おはよう!元気だよ。ありがとうね。(笑顔)」
②D様との会話
職員A:「D様、おはようございます。体調はいかがですか?」
D様 :「・・・・。(暗い表情)」
職員からの「おはようございます。」との声掛けに、K様は笑顔で返答があり、「お元気そうだな」と感じ取ることができます。一方で、D様は表情が暗く返事がありません。この様子から職員は、「D様は元気のない表情だな。心配事があるのかな?それとも体調が悪いのかな?」などと感じ取り、必要に応じて他職員と情報共有、対応することができます。
小さな変化に気づきアクシデントやトラブルを未然に防ぐ
きちんとコミュニケーションが取れていると、利用者様の心身の小さな変化に気づくことができます。また、それを職員間で情報共有することで、職場全体で利用者様に適切なケアを提供できるようになり、またアクシデントの防止にもつながります。
事例を見てみましょう。
【事例】介護職員AとY様との会話
職員A:「Y様、右足の痛みはいかがですか?」
Y様 :「実は昨日より痛くてね。歩くのがつらくなってきた・・・。」
Y様は右足の痛みとふらつきがみられます。職員Aは、すぐにY様から日常生活の様子や特にお困りの場所・場面などの具体的な情報を、コミュニケーションを取りながら収集し、その情報を他の介護職員や看護職員などの専門職員間で共有します。そして転倒防止のために、歩行時の介助方法の検討や、生活環境における危険個所を特定して必要に応じて障害物を撤去したり、段落部分に手すりを設置するなどの対策を行い、右足にかかる負荷も軽減しました。また、その後、医師の診察も受け、痛みの緩和につながりました。
高齢者とのコミュニケーションや会話で大切な4つのポイント
それでは、しっかりとコミュニケーションを取るためにはどうしたらよいのでしょうか?高齢者とのコミュニケーションで大切な4つのポイントをご紹介します。
会話では「聴き上手」になる
会話していると、つい話が自分主体になってしまうこともあるかもしれません。しかし、高齢者と会話をする際は、「話し上手」ではなく「聴き上手」であることを常に意識しましょう。
目を見てしっかり耳を傾け、相手のペースに合わせて「傾聴」することが大切です。傾聴することで、利用者様は安心感を感じて心を開き、もっと話したいという気持ちが湧いてきます。
相手の話を否定せず、受け入れて共感する
高齢者の中には同じ話を繰り返す方もいらっしゃいます。短期記憶力が低下しやすく「この人と話した」ということ自体が記憶から抜けてしまうことがあるためです。また、認知症の方は、職員を自分の子どもと間違えたり、お金を盗まれたなどと思って相談する場合もあります。
この時、共感や受容をするのは大変難しく、「そんなことはありません」などと否定したり、途中で話を遮ったりしてしまいがちです。しかし、この場合は、優しくあいづちを打ちながら最後まで傾聴し、その事実に対して有無の回答をしたり否定をするのではなく、ご本人のお気持ち(辛かった、怖かった、悲しかった、困ったなど)にフォーカスして共感しましょう。
そうすることで、「話を聞いてもらえている」と感じてもらうことができ、信頼関係の構築につながります。
高齢者の特性に対して正しい理解と知識を持つ
高齢者の特徴として、以下のような身体的特徴、心理的特徴があります。これらを把握・理解した上で接することで、コミュニケーション場面における配慮点がわかります。
身体的特徴
- 視力聴力の低下
- 感覚機能の低下
- 鈍化
- 物忘れ
- 免疫機能の低下 など
心理的特徴
- 短期記憶の低下
- 注意力集中力の保持低下
- 不安感 など
相手の尊厳を大切にする
介護現場で、利用者様に対して子どもに話しかけるような口調で話す職員をたまに見かけます。これは、自尊心を傷つけられるばかりではなく、ご本人の意欲低下にもつながりかねません。高齢者は人生の大先輩であり、どのような状況であっても「敬う心」を持って接するようにしましょう。きちんとした敬語や丁寧語を使い、相手を尊重する姿勢が大切です。
沈黙を恐れない
高齢者の中には、認知症や脳梗塞で言葉がスムーズに出ない方や難聴の方、会話が苦手な方などもいらっしゃいます。
話しかけても返事が無かったり、話題が思いつかず沈黙が続いてしまった経験はありませんか?
次の場合、どのように対応したらよいでしょうか?
【事例】E様(会話が苦手)を散歩に誘う介護職員Aとの会話
職員A:「今日はいいお天気ですね。E様、一緒に散歩しませんか?」
E様 :「・・・(笑顔でうなずく)。」
職員A:「紅葉がきれいですね。赤や黄色、Eさんは何色がお好きですか?」
E様 :「・・・。」
職員A:「どこかおすすめの紅葉の名所を御存知ですか?」
E様 :「・・・。」
職員A:「・・・。」
このような場合、無理に会話をしようとする必要はありません。職員が焦って質問を続けると、かえってE様のストレスになることも考えられます。
笑顔で散歩を受け入れて下さったE様です。沈黙が続いても焦らず、一緒の時間を共有しましょう。
会話をせず、ただ傍らに寄り添うことも大切なコミュニケーションの一つです。
高齢者とのコミュニケーションや会話のポイント

高齢者とのコミュニケーションを取るときに意識すべきポイントは何でしょうか?ここではすぐに実践できる内容を4つご紹介します。
声のトーンを低くし、ゆっくり、はっきり話す
高齢になると高い音や電子音が聞こえにくくなる傾向があり、言葉の理解に時間がかかる場合があります。
そのため、声のトーンを低くし、ゆっくり、はっきりと話しましょう。
また、相手が理解しやすいように、一度にたくさんのことを話さず、区切りながら簡潔に話すこともポイントです。
目線を合わせる
コミュニケーションを取る際は、相手と目線を合わせることが大切です。
目線がずれていたり、見下ろす位置から話しかけると、相手が疲れたり高圧的に感じられる可能性があります。
車椅子に座っている方、ベッド上で寝返りが難しい方など、相手が無理なくコミュニケーションを楽しむことができるよう、しゃがんだり傍らに座ったりして、相手との位置関係(横並び又は斜め横など)に配慮しましょう。そうして、相手が目線で語りかけてくれていることに気づき、その視線の先にある景色や様子に興味を持ち、言葉にしてみることで、コミュニケーションにつながることがあります。
共感してあいづちを打つ
会話をしているとき、人は相手が共感してくれると嬉しくなります。
相手の目を見て「あいづちを打つ」という動作は、「自分の話に興味を持って聞いてくれている」という印象と安心感を与え、「もっと話したい」という気持ちを起こさせます。
高齢者とのコミュニケーションでは、価値観の違いやギャップを感じたり、話がかみ合わない場面もありますが、相手のペースに合わせてあいづちを打つことを心掛けましょう。
表情・仕草に気を配る
高齢者とコミュニケーションをする際は、表情や仕草にも気を配りましょう。
やさしい笑顔と仕草は、安心感と話す喜びにつながります。
介護現場では職員がマスクを着用することも多く、口元が見えず表情が相手に伝わりにくくなります。そのため、笑顔の時は特に、目元も意識して表情を作りましょう。言葉遣いや話し方だけでなく、表情や仕草にもあなたの気持ちが表れ、相手に伝わります。
非言語的コミュニケーションも大切
2種類のコミュニケーション方法とポイント
コミュニケーションには、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションの2種類あることをご存知でしょうか?
ここではそれぞれの特徴についてご紹介します。
言語的コミュニケーション
言語的コミュニケーションとは、話す・聞く・書く・読むという実際に言語を使うコミュニケーションです。
ポイントは、まずは笑顔で明るくハキハキと話すこと。そして正しく丁寧な日本語と敬語を心がけることです。また、高齢者の身体や精神状態に配慮し、思いやりのある言葉を選ぶことも大切です。相手の状態やペースに合わせて声のトーン・口調・話すスピードに気を配りましょう。
非言語的コミュニケーション
非言語的コミュニケーションとは、表情、ジェスチャー、声のトーンなど、言葉以外の視覚や聴覚を通してコミュニケーションを取ることです。
1971年に心理学者アルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」では、人と人とのコミュニケーションにおいて、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%のウェイトで影響を与えるとされています。
つまり、実際の言葉を介さなくても、表情やジェスチャー、声のトーンなどでも十分に相手に意図や気持ちが伝わるということです。
非言語的コミュニケーションの事例を見てみましょう。
【事例】職員AとF様(脳梗塞の後遺症で右半身に麻痺、失語症)の更衣介助での会話
介護職員Aが、ベッドサイドでF様の目の高さに姿勢を落とし、声掛けをする。
職員A:「F様、着替えましょう」
F様 :「(笑顔とうなずき)」
職員A:「今日はどの服を着ましょうか?」
職員Aは、複数の上着を一つずつ指さし、ご希望を確認
F様 :「(希望の上着を指した時にうなずき)」
職員Aは、F様のご希望の衣類を確認し、最後に右手でOKサインをする。
この事例では、F様は失語症で話すことが難しいため、職員Aはうなずきなどのジェスチャーで意思表示ができるように衣類を指しながら確認をしています。そして、F様は質問に対し、笑顔(表情)やうなずきで回答しています。
このように、利用者様の特徴に合わせて、非言語的コミュニケーションも活用しましょう。
まとめ

介護現場において、利用者様との信頼関係を築き質の高い介護サービスを提供するためには、高齢者とのコミュニケーションはとても大切です。
「何を話したら良いか・・・」など、話す話題に注意が向きがちですが、大切なのはコミュニケーションに対する相手への姿勢です。表情や仕草などを意識して、話題や環境などに合わせた姿勢や位置関係、声のトーン、距離感などに注意しましょう。また相手の話に対して興味関心をもって傾聴し、お気持ちや意見を受容、そして感情に共感しましょう。相手に寄り添った相互のコミュニケーションを心掛けることで、信頼関係の構築、体調や精神面の変化に気づきアクシデントやトラブルの防止につなげることができます。
この記事をシェアする
人気記事ランキング
Ranking
ALL
週間
カテゴリー
Category
人気のキーワード
Keywords









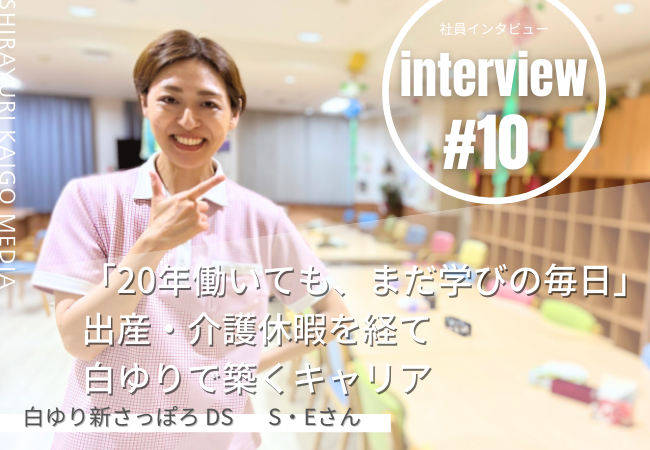




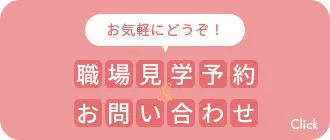





白ゆり介護メディア編集部
いかに白ゆりの魅力を伝えるかを常日頃考えている介護メディア担当です。
白ゆりの魅力と一緒に、介護職の皆さんのプラスになる知識やお悩みの解決につながる情報も発信しています。