介護のマメ知識
公開 / 最終更新
認知症の方とのコミュニケーションのポイント、介護施設での症状別の対応方法も解説!

介護現場で働いている介護職の方やこれから介護職を目指す方の中には「認知症の方とどうやってコミュニケーションをとったらいいか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
また「認知症ケアは大変、難しい」と感じる方もいるかもしれません。しかし、相手をひとりの人間として尊重し、心に寄り添うことが、笑顔を引き出すケアの鍵です。
この記事は、認知症の方とのコミュニケーションを取る際のポイントや、症状別の対応方法について解説します。介護職の方やこれから介護の仕事への転職や就職を検討されている方の参考になれば幸いです。
1分で予約・お問い合わせ完了♪
認知症の高齢者と向き合う時の心構え
認知症ケアでは、認知症の種類や症状について理解して関わることが大切です。
以下で解説する、代表的な4つの認知症や認知症の症状について理解しておきましょう。
認知症の代表的な4つの種類を理解する
認知症にはアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などの種類があり、それぞれ症状や進行の度合い、適切な対応が異なります。 それぞれの違いを理解した上でのコミュニケーションが必要となります。
・アルツハイマー型認知症
脳の正常な神経細胞が徐々に壊れ、記憶力や判断力が低下する割合が最も大きい認知症です。初期は物忘れから始まり、緩やかに進行するのが特徴です。進行すると 時間や場所等の見当識障害などの症状がおこり、日常生活に支障が出て介助が必要となります。
・脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血など脳の血管への障害によって起こります。アルツハイマー型認知症と同様に記憶障害などがみられますが、 脳の血管の障害を受けた部位の持つ機能分野によって症状が違うことが特徴的です(麻痺の部位、言語障害、運動障害)。また、しばらく状態が安定しますが、新たな脳血管障害が起きると、再び悪化する段階状に進行していきます。
・レビー小体型認知症
脳の神経細胞に異常なたんぱく質が溜まることで生じます。認知機能の低下に加えて、 幻視やせん妄、パーキンソン病のような症状(手足の震え、動作の緩慢など)を伴うことが特徴です。
・前頭側頭型認知症
前頭葉や側頭葉が委縮することで起こる認知症です。 人格の変化や社会性の低下、言語機能の低下などがみられます。
中核症状とBPSD(行動・心理症状)の違いを理解する
次に認知症の症状ですが、認知症の症状は、大きく以下の2つに分けられます。
・中核症状
記憶障害や見当識障害(場所や時間がわからなくなる)、言語障害、失行、失認など、脳の神経細胞の障害によって起きる症状のことです。
・BPSD(行動・心理症状)
徘徊や不眠、帰宅願望・暴言・暴力・もの盗られ妄想など、中核症状に伴って現れる心理的症状や行動障害のことで、認知症の直接的な症状ではないものの生活に大きな影響を与える症状です。
認知症は人によって症状や進行の度合いが異なりますが、同じ認知症の方でも、その日の時間帯や体調、状況によってさまざまです。その方の個性や状況に応じたコミュニケーションを取ることが重要になります。
認知症の方とより良い関係を築くためのコミュニケーションのポイント

認知症の方との会話が苦手だと感じる方もいらっしゃいますが、ちょっとした工夫で笑顔が生まれることもあります。
認知症の方とコミュニケーションをとる際のポイントは以下のとおりです。
耳元でゆっくりはっきり穏やかに話す
年齢を重ねると、老化によって聴力が低下して聞こえにくい場合があり、相手が何を話しているか分からないと不安に感じることがあります。
相手のペースに合わせ、声が相手に届くように耳元で話し、相手が聞き取りやすいようにゆっくりはっきりと話すと、伝わりやすいです。
特に、騒がしい環境やマスクをしている場合は、声のトーンや話し方にも工夫しましょう。
シンプルでわかりやすい言葉で話す
会話をしている時、人は話している言葉や前後関係、情報の保持をする必要がありますが、認知症の方は、記憶を保持することが難しくなっています。そのため、一度にたくさんのことを伝えたり、難しい言葉を使ったりすると、混乱を招き、ストレスを感じさせてしまうことがあります。
短い文章でゆっくり、一つずつ順番に伝えることがポイントです。また、わかりやすい言葉で伝える、本人にとって馴染みの言葉を使う、必要に応じて実際の物や絵を見て頂きながら伝える、ジェスチャーを交えて言語と視覚両方へ働きかけるなど、話し方の工夫もしましょう。
視線を合わせ穏やかな表情で接する
会話をする時には相手との距離感や位置関係が重要です。相手の目を見て話すことで「自分と話している」と感じ、相手は安心感を得ることができます。
介護は、目線を合わせて会話することが基本ですが、特に車いすやベッドに横になっている方と会話するときは、立ったままのコミュニケーションに注意が必要です。
上からのコミュニケーションは相手が見下されていると感じやすく、不安や不快感につながる恐れがあります。
お互いの表情や気持ちが伝わるように、目線を合わせたコミュニケーションに配慮しましょう。
相手の気持ちに寄り添い、共感する姿勢で接する
認知症の方との会話では、時には事実とは異なることを話したり、会話が嚙み合わなくなることもあるかと思います。
しかし「そんなことはありません」「それは違います」といった、表面的な言葉に対する否定的・批判的な言葉をかけると関係性が不安定になり、また認知症の方の心は孤立して傷つきやすくなります。事実関係の判断にこだわるのではなく、 なぜそのようにお話されるのか、その背景や理由を知るためのコミュニケーションに注力しましょう。そのためにも、「不安な気持ち、よく分かります。それはお辛かったですね。一緒にどうしたらいいか考えていきましょう。」と、お話を受容し、気持ちに共感する姿勢で対応することが大切です。
相手の気持ちに共感する姿勢で接することで、相手は「自分のことを理解してくれている」と感じ、より深い信頼関係を築くことができます。
相手の気持ちを受け入れることで、相手も心を開き、円滑なコミュニケーションが取れるでしょう。
過去の記憶や得意なことを話題にする
生活歴等をもとに、昔好きだったことや得意だったこと、お仕事や生まれ育った地域や環境のことを話題にすると、安心感が生まれ言葉を引き出すことが出来ます。例えばお花の雑誌を見ながら「お花が好きで、お庭で沢山育てていたと聞きました、どんなお花を育てていましたか?」、また「編み物が得意で、家族に編んであげていたと聞きました!どんな物を作っていましたか?」など、相手の経験を尊重した会話を意識すると良いでしょう。
これらのポイントを意識することで、認知症の方との関係がよりスムーズで温かいものになるでしょう。
認知症の方の症状別の接し方
認知症の症状は、人によってさまざまで、同じ認知症の方でも、日によって症状が変化することがあります。
ここでは、いくつかの認知症の症状別の接し方についてみていきましょう。
被害妄想(もの盗られ妄想など)
被害妄想は、実際には起こっていないことを本人が信じることです。その一つのもの盗られ妄想は、実際に盗まれていないにも関わらず、「私の財布が盗まれた!」など、盗まれたと思い込んでしまう状態です。
「盗まれていませんよ」といった否定的な態度ではなく、「大変でしたね。一緒に探しましょうか?」と訴えに共感し、対応しましょう。
また、一緒に探し行動を共にして本人が心配している本当の理由を探りながら、「心配」から「安心」へ気持ちが切り替わるような視点を変えた会話をしたり、タイミングを図って見つけて安心を共有したり、見つけやすい場所に置き本人に見つけてもらうのも一つの方法です。同じ視点からのコミュニケーションを図り自尊心が傷つかないような配慮をすることが大切です。
帰宅願望
「家に帰りたい」と何度も繰り返し言ったり、実際に施設から出ようとする帰宅願望の行動が見られることがあります。記憶の混乱や認識のズレによる言動を否定・訂正をしたり、無理に行動を制限すると、かえって不安が増大し、症状悪化の恐れがあるため、 相手の訴えを受容し、帰りたい理由やその背景を探る言葉かけをして想いに耳を傾けることが重要です。
「家まで送りますよ」と声をかけて一緒に歩き、少ししたら「そろそろ帰りましょう」と誘導することで安心される方も多くいらっしゃいます。
また「今日はもう遅いから泊まっていきませんか?」など、選択肢のある声かけも良いでしょう。
食事したことを忘れている
認知症の方の中には、食事したことを忘れ「まだ食べていない」と訴える方も多い傾向です。本人は、本当に食べていないと思っているので「もう食べましたよ」と否定すると、さらに訴えが強くなる可能性があります。
相手の気持ちを尊重し、「今準備しているのでもう少しお待ちくださいね」などと穏やかな声かけをする、支度を手伝っていただく、栄養バランスを考えながら軽食をとっていただく、お飲み物を提供するなどして、少し時間を置いてから再び声をかけてみると落ち着くこともあるでしょう。
攻撃的な言動がある
認知症の方の中には、攻撃的な言動がある方もいますが、これは認知症機能に伴うBPSD(行動・心理症状)の症状の一つです。
本人が意図的に行っているわけではなく、伝えたいことがうまく言葉にできず、もどかしい気持ちや不安が、攻撃的な言動として表れてしまうことがあります。
攻撃的な言動の理由は、以下のようにさまざまです。
- 自尊心が傷つけられたと感じている
- 自分の気持ちを理解してもらえないと感じている
- 行動が制限されていると感じている
- 環境の変化に戸惑っている
- 不安や不快な気持ちを感じている
- 過去の経験や性格が影響している
攻撃的な言動があるとき、無理な声かけや、行動を遮るようにして落ち着かせようとすると、逆効果になってしまうことがあります。 まずは本人や周囲の環境の安全を確保し、本人の言動を観察、要因となっている理由を探りましょう。腹痛などの痛みや違和感が要因とわかれば解消できる方法を、不安にさせる刺激となるような光や音・臭い・物・影などがあれば撤去する、静かな環境や本人が落ち着いて過ごせる場所へ移動したり対応する人を変えるなどの対応を試してみましょう。
認知症の方とのコミュニケーションで注意すべきこと
認知症は「今までできていたことが難しくなった」「覚えていたはずなのに忘れてしまう」など日常生活に大きな不安をもたらします。
介護職の方にとってはどう対応したら良いかと感じる大変難しいケアとして捉えがちですが、認知症という病気の影響であり、本人の意図的な言動ではありません。介護者のコミュニケーションによって、認知症のQOL(生活の質)に大きく影響します。
認知症の方とコミュニケーションをとる際は、以下のポイントに注意しましょう。
否定したり叱ったりしない
認知症の方の言動は、私たちから見ると理解しにくい場合もありますが、本人にとっては現実として感じていることです。
言動の否定や叱責は、不安感を与え、自尊心を傷つける行動です。訴えに耳を傾け、尊厳を守り相手を尊重した声かけを行いましょう。
無視や放置をしない
認知症の方の中には、同じ質問や話を何度も繰り返す方も多い傾向です。「また同じことを言っている」「いつものことだから」と、無視や放置は、孤独感や不安感を与え、症状の悪化を招く恐れがあります。
相手の話を最後まで聞き「〇〇さんは、〇〇が心配なのですね」など、相手の気持ちに寄り添う言葉をかけ、安心できるケアを心掛けましょう。
細かい指示や命令をしない
認知症の方の中には、場所が分からなくなったり、日常生活の動作が難しくなる方もいます。
例えば、排泄の動作が分からない、食事中にこぼしてしまう、トイレを探して他の入居者様の部屋を開けるなど、介護現場では、ヒヤリとするシーンもあるでしょう。しかし「〇〇をして、次に〇〇をして」といった細かい指示や、「動かないで」「早くして」などの命令は、不安感や威圧感から信頼関係に影響を及ぼすことがあります。
動作を促す際の声かけは、一つの動作ごとに短く伝えたり、「一緒にしましょうか」「急がなくていいですよ」と、相手が落ち着いて行動できるような声かけを意識することが重要です。
まとめ
認知症の方とのコミュニケーションを取る際のポイントや、よくある症状別の対応方法について解説しました。
認知症の方は、大事な人のことを忘れてしまったり、日常の動作が分からなくなってしまったりと、さまざまな不安や喪失感と日々向き合っています。大切なことは「認知症だから」と決めつけたり訴えを否定したりせず、その方の心の奥にある不安や孤独感に寄り添い、心のつながりを築くことです。
今回の記事を参考にしていただき、認知症に関する理解を深め、より良いケアに取り組んでいきましょう。
この記事をシェアする
人気記事ランキング
Ranking
ALL
週間
カテゴリー
Category
人気のキーワード
Keywords





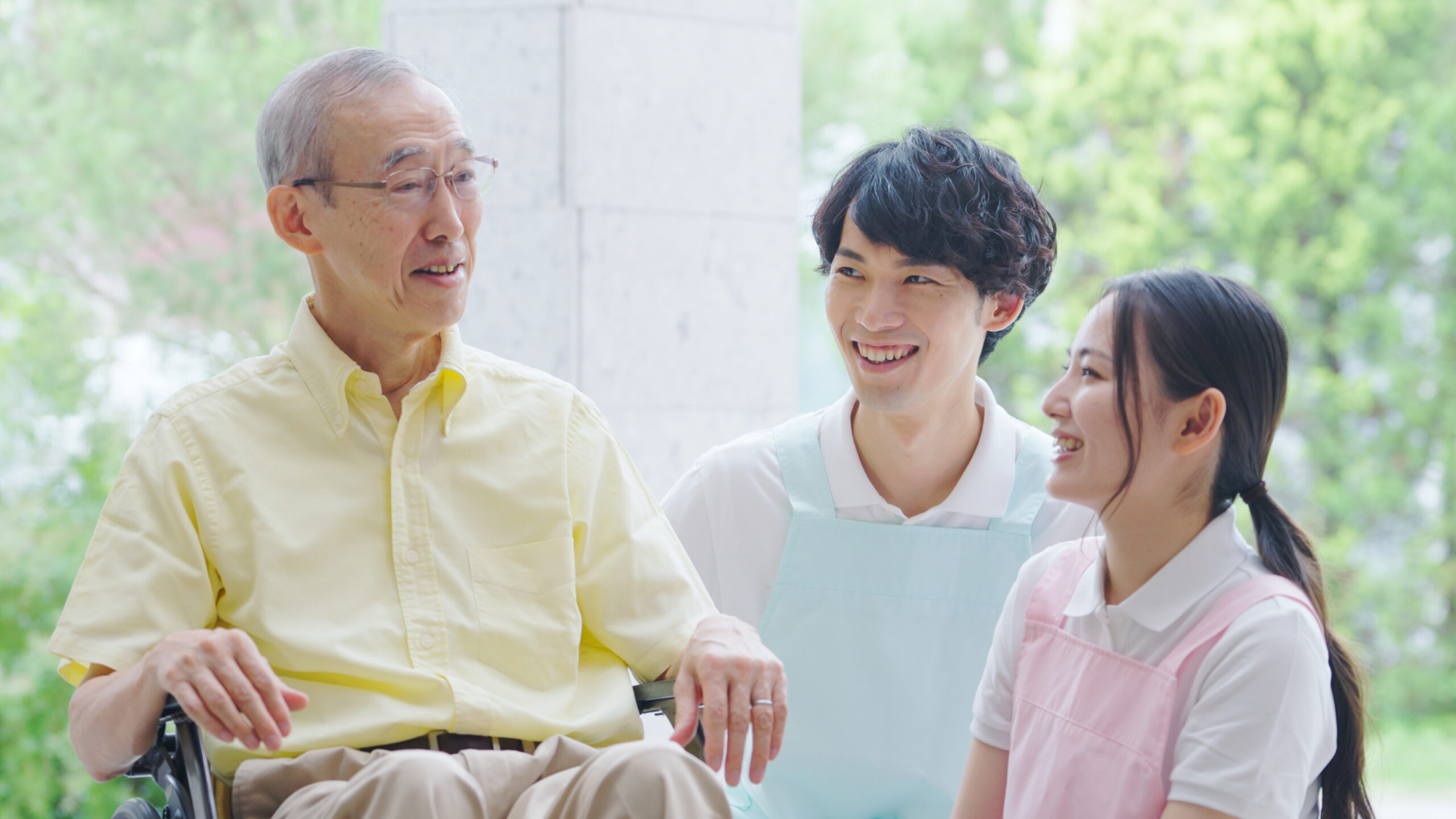








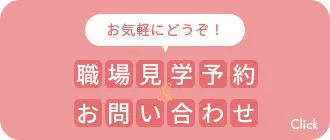





白ゆり介護メディア編集部
いかに白ゆりの魅力を伝えるかを常日頃考えている介護メディア担当です。
白ゆりの魅力と一緒に、介護職の皆さんのプラスになる知識やお悩みの解決につながる情報も発信しています。